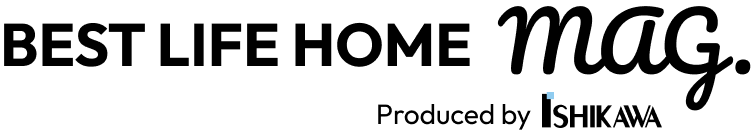建売と注文住宅で住宅の寿命や品質に違いがあるのか疑問に思ったことはありませんか?
結論からお伝えしますと、建売住宅の寿命は等級によって異なります。
住宅の寿命は一律で何年と決まっているのではなく、劣化対策等級という建物を長持ちさせるための対策を評価する項目によって、おおよその目安が定められているのです。
そこで本記事では、新潟県注文住宅建築棟数15年連続No.1のトスケンホームが建売住宅の寿命や注文住宅との違い、長期的に安心して暮らすためのメンテナンスを詳しく解説していきます。
住宅選びで悩んでいる方、建売の寿命や品質について知りたい方はぜひお読みください。
建売住宅の寿命の目安は等級によって異なる

住宅の寿命を考える上で覚えておきたい用語として「劣化対策等級」があります。
劣化対策等級は、「建物の骨組み部分の劣化対策(=長持ちするための対策)」を評価する項目です。
日本住宅性能表示基準では以下の3等級に分けられています。
- 等級1→建築基準法に定める対策が講じられている(およそ30年程度)
- 等級2→2世代(50年〜60年程度)まで長持ちする対策が講じられている
- 等級3→3世代(75年〜90年程度)まで長持ちする対策が講じられている
建物の寿命は、これらの等級を目安に考えましょう。
なお、トスケンホームが提供する建売住宅は、劣化対策等級3の条件をクリアしているので、安心して住んでいただけます。
劣化対策等級については、「劣化対策等級とは?木造住宅の耐用年数や等級1・2・3の違いを紹介」にて詳しく解説をしています。

寿命の目安(劣化対策等級)と耐用年数の違い
劣化対策等級と混同しがちなのが「耐用年数(法定耐用年数)」です。
耐用年数は住宅の構造ごとに年数が定められています。
例えば木造住宅の法定耐用年数は22年、RC造住宅は47年などです。
これらは建物自体の寿命ではなく「減価償却の計算用の数字」です。
固定資産税や住宅ローン審査で用いるものなので、混同しないよう注意しましょう。
なお、建物の法定耐用年数は国税庁HPで確認できます。
建売住宅と注文住宅との寿命の違いはない

「建売は注文住宅より寿命が短い」という噂を聞いたことがあるかもしれませんが、これは誤りです。
どちらも「建築基準法」「住宅品確法」に従って建てられており、寿命に違いはありません。
「建築基準法」は、住宅の耐震性や耐久性を保つための法律です。
建売と注文住宅はどちらもこの法律に則った、同じ検査が実施されます。
「住宅品確法」は引き渡しから10年保証を義務付けた法律であり、建売・注文どちらにも適用されます。
ではなぜ「建売は注文住宅より寿命が短い」という誤解が生まれたのでしょうか?
建売は寿命が短いと言われる理由
誤解の原因は、高度経済成長期に建築された建売にあると言われています。
当時は今のように、住宅の品質を守るための法律が整備されていませんでした。
また、好景気の影響で住宅は建てればいくらでも売れる時代でした。
現場では早く安く、たくさんの住宅を提供することが求められます。
その結果、耐震性や耐久性の低い建売が市場に出回り「建売は寿命が短い」と言われるようになりました。
しかしこれは、建築基準法が大きく改正される1981年以前の話です。
現在の建売は建築基準法や住宅品確法に則って建てられており、注文住宅と同じ品質で提供されています。
建売住宅の寿命に影響を与える要素とは?

建売の寿命に影響を与える要素は大きく3つあります。
- 地盤や土地
- 劣化対策等級や住宅性能表示制度
- 購入後のメンテナンス
以下で詳しく説明しますので、住宅を選ぶ際の参考にしてください。
地盤や土地
地盤や土地が頑丈な場所に建てられた住宅は、寿命が長くなりやすいと言われています。
地盤が軟弱だと地盤沈下で建物が傾くなどの問題が発生する恐れがあります。
購入前に地図や自治体のWebサイトで地盤や土地の強さを確認しましょう。
劣化対策等級や住宅性能表示制度の確認
寿命を考える上で「住宅性能表示制度」に対応しているか確認するのも一つの方法です。
住宅性能表示制度は、住宅の劣化対応を表す「劣化対策等級」や構造の安全性を示す「耐震等級」などの性能を示す制度です。
この制度を取り入れている住宅であれば、客観的な評価基準に基づいて、住宅の性能評価を知ることができます。
また、耐震等級については、「耐震等級3と1ではどう違う?調べ方や後悔しないためのポイントを解説!」にて詳しく解説をしています。

購入後のメンテナンス
購入後のメンテナンスも、寿命を延ばす上で重要です。
特に屋根や外壁など建物の外部は定期的なメンテナンスの実施が鍵を握ります。
また、水回りの設備交換、木材のシロアリ対策なども定期的に必要です。
メンテナンスを適切に施すことで、次の世代も住める家にしていきたいですね。
建売住宅の寿命を延ばすために必要なメンテナンス
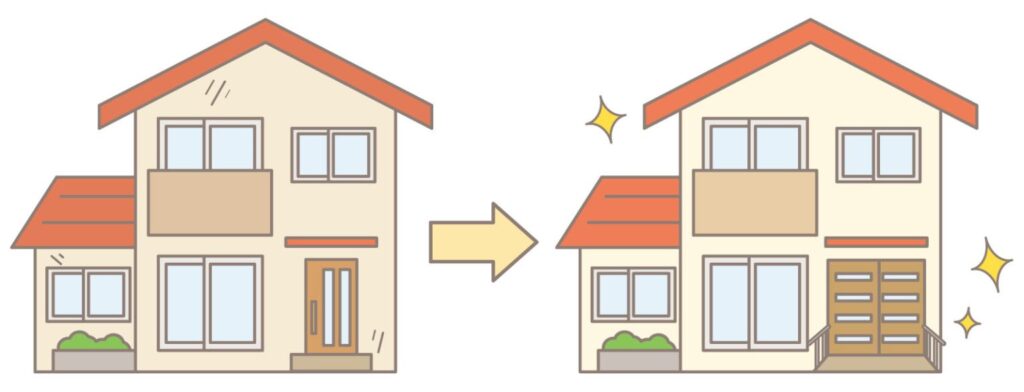
建売の寿命を延ばし、末永く快適に暮らすためには、以下の3つのメンテナンスが不可欠です。
- 外壁や屋根の塗装・修繕
- 水回りの設備の更新
- シロアリ対策
それぞれのメンテナンス方法について以下で解説します。
外壁や屋根の塗装および修繕
外壁や屋根は10年ごとのメンテナンスが推奨されています。
外壁はヒビ割れがないか確認したり、指で触って粉がつくかチェックしましょう。
粉がつく場合はメンテナンスが必要な時期と判断できます。
屋根は、外から見て屋根材が浮いていないか、ヒビ割れがないか確認してください。
水回りの設備の更新
水回りの設備は、新築から10年〜15年程度でメンテナンスをすることが推奨されています。
水道や配管、キッチン、浴室、給湯器などの設備をチェックしましょう。
給湯器の交換目安は15年と言われているため、故障の前に交換することをおすすめします。
シロアリ対策
建物の寿命を延ばす上で忘れてはならないのがシロアリ対策です。
シロアリは木材をエサとして生息し、床下などに巣を作ります。
一度住み着くと駆除するまで移動しないため、定期的な対策が必要です。
一般的にシロアリ駆除の頻度は5年に1回と言われています。
新築の場合は住み始めて5年目に、最初のシロアリ対策を行いましょう。
建売住宅購入前に保証内容の確認を

建売住宅を購入する際には、メンテナンスだけでなく保証内容の確認も重要です。
保証内容は、住宅の品質や将来の安心感に直結するため、慎重にチェックする必要があります。
特に、「保証期間」と「補償の対象範囲」はハウスメーカーによって異なります。
購入を検討している方は必ず確認をしてください。
トスケンホームでは、安心して住宅を購入できるよう「暮らしの4大保証」をご用意しています。
まとめ
建売の寿命は、建物の品質やメンテナンスの状態によって異なることがご理解いただけたかと思います。
建売と注文住宅の寿命には特別な違いはありません。
どちらも建築基準法に基づいた確認・検査が義務付けられています。
住宅の寿命を最も左右するのはメンテナンスです。
購入後の定期的なメンテナンスによって建売住宅の寿命を延ばすことができます。
なお、弊社トスケンホームでは、末永く快適に住んでいただくための4大保証をご用意しています。
新潟県内で住宅購入をご検討中の方、いつでもお気軽にご相談ください。